リハビリテーションの重要性
前回もお話しした通りパーキンソン病は根本的な治療方法がなく、完治ができない病気です。
その為対処療法が中心となりますが、
投薬治療、外科的治療とあわせて
身体機能を維持するために必要な治療のひとつが
リハビリテーションです。
パーキンソン病は無動症状、姿勢反射障害が起こるため
リハビリテーションを意識的に行っていかないと
運動不足になりがちで病気の進行以上に身体機能の低下が
発生しやすい病気です。
体は定期的に動かすことで、
機能が維持されたり向上したりします。
パーキンソン病治療と合わせて
認知機能にも良い影響がありますので
継続して取り組んでいきましょう。
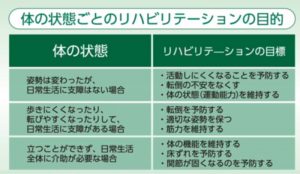
リハビリテーションは下記の4つの内容が
中心となります
1 歩行訓練
病気の進行とともに体が上手く動かせなくなるため
歩行を上手くできるようする工夫をして行いましょう。
メトロノームを使用したり、床にテープで歩幅の目安を
つけたり、「1.2」や「右.左」等の掛け声をかけたりする方法が
お勧めです。
2 運動療法
関節や筋肉が硬くなる症状の進行を防ぐため
全身の筋肉を伸ばすストレッチが運動を行います。
生活を送る上で必要な筋力を維持するために重要な
リハビリです。
3 呼吸訓練
病状の進行に伴って姿勢が前屈みになることが多い為
肺や気管を圧迫して呼吸がしずらくなります。
姿勢を正し、深呼吸を定期的に行う事で
症状の改善を図ります。吹き戻しの様な
物を利用して呼吸のリズムを意識させる方法も
お勧めです。
4 言葉の訓練
筋肉が硬くなる事で口が明けにくくなったり
お腹に力が入りにくくなったりすることで
声が出しにくくなったり、感情が入らなくなるようになります。
大きく口をあけてゆっくり文章を読み上げたりすることで
スムーズに発声できるようにします。
自宅で行える体操
リハビリといっても特別な器具を
使う必要はありません。椅子に座ったり
寝転んだ状態でできる事を中心に行っていきましょう。
顔の体操
顔の筋肉のこわばりやしゃべりにくさを改善します。
・口を大きくあけたりすぼめたりする
・顔をしかめたり、笑顔を作ったりする
・頬を膨らませたり戻したりする
・舌で唇の周りをなめる
・ア、イ、ウ、エ、オの音を大きな声で
はっきり発音する
・パ・タ・カ・ラと はっきり発音し繰り返す
頭と首の体操
首の運動は、痛みがでない程度に行いましょう。
・頭をゆっくりと左右にうごかす
・頭を左右にゆっくりまわす
肩・腕・手・指の運動
関節の柔軟性を高めて動かしやすくします。
・両手を合わせ腕をゆっくり上げる
・手を背中の後ろで振り上げ下げをする
・両手を腕の前で合わせ手首を左右に倒す
・腕おあげ手を握ったり開いたりする
立って行う運動
両足を10~20cm開くと体が安定します。
・肩幅くらいに足を開いて立ち、ゆっくり身体を前にまげる
・身体をゆっくり左右にひねる
・壁を背にして立ち、背中の前面が壁につくように胸をはる
・壁に向かって立ち、両手を壁にあてながら背中を伸ばす
座って行う運動
・両足の膝をたて、お尻を床から離したり戻したりする
・両足の膝をたて、両足を左右にゆっくりひねる
・うつぶせになり、両肘を床について背中を伸ばす
日常生活の工夫
パーキンソン病の病状の進行に伴って
日常生活が困難になってきますその中で
「自分のことはできるだけ自分で行う」ことは
それだけでもリハビリテーションになります。
色々と工夫をする事でできるだけ自分の事は
自分でできるように環境を整える事が大切です。

食事の時
病状の進行に伴って嚥下力が低下し
食べ物の飲み込みが悪くなりがちです。
食材を細かく刻んだり、調理法を工夫しましょう。
液状のものは肺に入ると誤飲性肺炎を発症する可能性が
ありますのでむせる状態が続くようなら
トロミをつけてから飲むようにしましょう。
箸の操作が困難な場合、太柄のスプーン・フォークへの変更や
安定感のある割れない食器の使用するのもお勧めです。
入浴の時
狭いところでは急に動きが悪くなる場合があります。
水周りでは特に滑りやすい状態のため、シャワーチェアーや
すのこ、手すり等を必要な場所に早めに準備しておきましょう。
まとめ
説明してきた内容を確認していただければわかるとおり
リハビリといっても特別な事をする必要はありません。
日常生活で自分でできる事をできる限り自分でやるという事を
意識して主体性をもって行っていってください。
